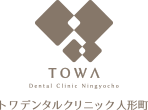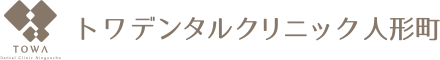あなたのお子様は大丈夫?上唇小帯や舌小帯について
2024.05.10
上唇小帯や舌小帯の改善は
いつ頃がよい?
**上唇小帯(じょうしんしょうたい)や舌小帯(ぜつしょうたい)**の状態が原因で、授乳や発音、歯並びに影響が出る場合があります。これらの改善(必要に応じた処置)は、症状や成長の状況に応じてタイミングが異なります。この記事では、それぞれのケースについてわかりやすく説明します。
上唇小帯とは?
上唇小帯は、上唇と歯茎をつなぐ薄い膜のことです。この部分が短すぎたり、厚みがある場合、次のような影響が出ることがあります。
- 前歯のすき間(正中離開)
- 歯並びの不正
- 歯ブラシが当てにくく虫歯リスクが高まる
改善のタイミング
- 乳歯列期(2~6歳頃)
この時期に特に問題がなければ様子を見ます。 - 永久歯列期(7歳以降)
前歯が生えそろった時点で自然にすき間が閉じない場合や、矯正治療の妨げになる場合に処置が検討されます。
舌小帯とは?
舌小帯は、舌の裏側と口腔底をつなぐ膜です。舌小帯が短い場合は「舌小帯短縮症(ぜつしょうたい たんしゅくしょう)」とも呼ばれ、以下のような問題を引き起こすことがあります。
- 授乳の障害(乳幼児期)
- 発音の問題(特に「ら行」「た行」)
- 食事の際に舌がうまく動かせない
改善のタイミング
- 乳幼児期
授乳がスムーズにできない場合は早期の改善が必要です。新生児や乳児の段階での対応が一般的です。 - 幼児期以降
発音や舌の動きに支障がある場合に処置を検討します。ただし、発音の改善には処置後も言語療法が必要な場合があります。
上唇小帯と舌小帯の改善は
必要?
上唇小帯や舌小帯は、すべての人に必ず処置が必要なわけではありません。
症状がない場合や成長とともに自然に改善するケースも多くあります。お子さんの状態が気になる場合は、まず歯科医師や小児歯科専門医に相談して、必要かどうかを見極めてもらいましょう。
まとめ
- 上唇小帯の改善は、歯並びや矯正治療への影響を考慮し、7歳以降に判断するのが一般的です。
- 舌小帯の改善は、授乳の障害がある場合は早めに対応し、発音や舌の動きの問題があれば幼児期以降に検討します。
気になる症状があれば、無理に判断せずに専門家にご相談ください。早めのチェックが大切です。
人形町の歯医者のトワデンタルクリニック人形町では、お子さんの口腔機能の発達に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお声がけください!