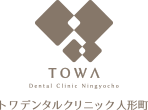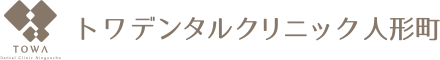親知らずの抜歯に「2回法」があるって知っていましたか?
こんにちは。
歯医者さんで「親知らずを抜きましょう」と言われたことがある方、多いのではないでしょうか?
「腫れるのが心配…」「痛そうで怖い…」そんな不安から、なかなか踏み出せない方もいらっしゃると思います。
今回は、そんな方に知っていただきたい「親知らずの2回法」という治療法について、わかりやすくご紹介します。
そもそも「親知らず」ってどんな歯?
親知らずは、上下左右の一番奥に生えてくる永久歯で、「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」とも呼ばれます。
多くの方は10代後半〜20代にかけて生えてきますが、まっすぐ生えずに横向きになったり、歯ぐきに埋まったままのことも多いのが特徴です。
こうした親知らずは、歯みがきが届きにくく、虫歯や歯周病の原因になったり、手前の歯を押して歯並びを悪くしたりすることがあります。そのため、抜歯をすすめられることがあります。
通常の抜歯と2回法の違いは?
一般的に親知らずの抜歯は、1回の処置で歯を取り除く「1回法」が主流です。
一方で、リスクを減らすために「2回に分けて」抜歯する方法があるのをご存知でしょうか?
それが「2回法」や「段階的抜歯」と呼ばれる方法です。
2回法ってどんな方法?
文字通り、「2回に分けて抜く方法」です。
- 1回目:親知らずの「歯の頭の部分(歯冠)」だけを切除します。
- 2回目(数ヶ月後):残った「歯の根っこの部分(歯根)」を抜き取ります。
この方法は、特に以下のようなケースで有効とされています:
- 歯の根っこが神経や血管に非常に近い
- 歯が骨の中に深く埋まっていて、無理に抜くと大きなダメージが出そうなとき
- すぐにすべてを取り除くと、腫れやしびれのリスクが高いと判断される場合
なぜ2回に分けるの?メリットと目的
神経へのダメージを防ぐため
下の親知らずの根の先端が、下あごの中を通る「下歯槽神経(かしそうしんけい)」という大切な神経に接していることがあります。無理に抜歯すると、まれにですが唇やあごの感覚が一時的または永久に麻痺してしまうリスクも。
2回法では、まず頭の部分だけを取ることで、根が少しずつ自然に骨の中で移動してきたり、吸収されたりするのを待つことができます。そうすることで、2回目の抜歯をより安全に行える可能性が高まります。
腫れや痛みの軽減
いきなり深い位置まで手を加えると、骨や周囲の組織に大きな刺激が加わり、腫れたり強い痛みが出ることがあります。2回に分けて少しずつ処置することで、術後の腫れや痛みを和らげられる可能性があります。
「怖さ」をやわらげる
「抜歯が怖くてどうしても踏み出せない…」という方にも、いきなり全部抜くのではなく段階的に処置することで、精神的なハードルがぐっと下がることがあります。
デメリットや注意点はあるの?
もちろん、2回法にも注意すべき点があります。
通院回数が増える
2回に分けて抜歯するため、当然ながら歯科医院への通院は増えます。
経過観察が必要
1回目の抜歯のあと、しばらく様子を見る期間があります。その間に腫れや痛みが出ることもあり、途中で計画を見直すこともあります。
すべてのケースに適応できるわけではない
2回法は万能ではなく、患者さん一人ひとりのお口の状態を見て判断する必要があります。浅く埋まっている親知らずや、感染を起こしている歯には適さない場合もあります。
2回法に向いているのはこんなケース
- ・親知らずの根が神経に近接していると診断された
- ・CT検査で抜歯リスクが高いと判断された
- ・無理に抜くと術後のダメージが大きくなりそうなケース
- ・安全に抜歯したい、という希望が強い方
最近は、CTスキャンなどの画像診断の精度が上がっており、リスクのあるケースを事前にしっかりと把握できるようになりました。その結果、2回法を提案される場面も増えてきています。
トワデンタルクリニック人形町での親知らず抜歯
当院では、親知らずの抜歯においても「できるだけ安全に・できるだけ負担少なく」をモットーに診療しています。
患者さんの状態に応じて、CT撮影を行い、神経や周囲の構造をしっかり確認した上で、1回法がよいのか2回法が適しているのかをご提案いたします。
「抜歯が怖い」「しびれのリスクが心配」など、不安なことがあればどんなことでもご相談ください。
まとめ
親知らずの抜歯は、決して「怖いもの」「我慢して受けるもの」ではありません。
治療の選択肢にはいくつかあり、「2回に分けて抜く」という方法も、安全性を高める大切な選択肢のひとつです。
すべての患者さんがこの方法を選ぶわけではありませんが、「自分にとって最も安心できる方法を選ぶ」ことが大切です。
親知らずについてお悩みの方は、ぜひ一度トワデンタルクリニック人形町にご相談くださいね。
あなたにとって最善の治療方法をご提案いたします。