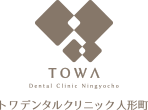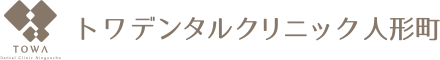- 安全な親知らずの抜歯を実現するための取り組み
- 親知らずを抜くべきかどうかの判断基準
- 親知らずの主な生え方
- 親知らずの抜歯後の腫れ・痛みの期間
- 抜歯当日にしない方が良い7つのこと
- 親知らずの抜歯の流れ
- ご自身の歯を移植する「自家歯牙移植」
- 「自家歯牙移植」のメリット
- 自家歯牙移植を適用できる条件
- 当院の自家歯牙移植
安全な親知らずの抜歯を
実現するための取り組み
必要最低限の切削での抜歯を可能にする
「CT撮影」による事前診断
 親知らずの抜歯には、神経や血管、周囲の骨との位置関係を正確に把握することが重要です。
親知らずの抜歯には、神経や血管、周囲の骨との位置関係を正確に把握することが重要です。
当院では、歯科用CTによる三次元画像を用いて、従来のレントゲンでは見えにくかった部分までしっかり確認した上で診断を行っています。
特に、顎の骨に埋もれた親知らず(埋伏歯)や、神経に近い位置にあるケースでは、CT画像が治療の安全性を大きく高めます。無理な切開や余分な骨の切除を避けられるため、術後の腫れや痛みといった負担も軽減しやすくなります。
下顎の奥には神経が通っているため、事前の綿密な診査・診断が欠かせません。当院ではCTデータをもとに丁寧な手術計画を立て、神経や血管を傷つけるリスクを最小限に抑えた抜歯を行っています。
術前の丁寧な説明と麻酔処置で痛みの軽減
「親知らずの抜歯=痛い・腫れる」というイメージから、不安を感じて来院を躊躇する方も多くいらっしゃいます。当院では、そうした不安を少しでも和らげられるよう、患者様のお気持ちに寄り添い、分かりやすい丁寧な説明を大切にしています。
麻酔処置についても、なるべく痛みを感じにくいよう配慮して行っています。お口の状態や抜歯の難易度、患者様の不安の程度などを踏まえ、できるだけ快適に処置を受けていただけるように麻酔の打ち方や量も細かく調整しています。
さらに、術後の腫れや痛みなどにも迅速に対応できるよう、ケア体制も整えております。抜歯後の過ごし方や注意点については、抜歯前にしっかりとご案内いたしますので、初めての方でも安心して治療に臨んでいただけます。分からないことや気になることがありましたら、お気軽にお尋ねください。
充実した術後のアフターケア
親知らずの抜歯は、術後の過ごし方も非常に大切です。当院では、治療が終わったあとも安心して日常生活に戻っていただけるよう、アフターケアにも丁寧に取り組んでいます。
抜歯後の経過をしっかり確認するため、術後には経過観察のための診察を行い、腫れや痛み、出血の有無などを丁寧にチェックしています。万が一トラブルがあった場合も、迅速に対応できる体制を整えております。
また、術後に気をつけたいことや、痛み・腫れをやわらげるためのコツ、食事や歯磨きの注意点なども分かりやすくお伝えしています。患者様が不安なく速やかに回復できるよう、術後も充実したサポートを行っています。
親知らずを抜くべきかどうかの判断基準
親知らずは、必ずしも抜かなければならない歯ではありません。真っすぐに生えていて、上下の歯がしっかり噛み合い、周囲の歯ぐきにも悪影響がないようであれば、そのまま経過を観察することも可能です。
ただし、次のような状態にある親知らずは、将来的なトラブルを回避するために抜歯を検討する必要があります。
- 手前の歯に向かって斜めに生えている
- 一部しか出ておらず、完全に歯ぐきから出てきていない
- 食べ物や汚れが溜まりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高い
- 過去に何度か歯ぐきが腫れたことがある
- 歯や歯ぐき、口の内側を傷つけてしまう可能性がある
- 含歯性嚢胞などの病変が疑われる
このような親知らずを放置すると、炎症が悪化し、顎の骨やその周囲にまで影響を及ぼすことがあります。場合によっては、顔全体の腫れや開口障害を起こしたり、呼吸に支障をきたしたり、命に関わる危険な状態へ発展することもあるので、注意が必要です。
親知らずの状態を正確に診断し、リスクがあると判断された場合には、早めの抜歯が望ましいです。診断結果に応じて最適なタイミングをご提案しますので、ご不安な方はぜひ一度ご相談ください。
親知らずの主な生え方
まっすぐ生えている親知らず
親知らずが上下に真っ直ぐ生えていて、かみ合わせにも問題がなく、炎症や痛みなどの症状が出ていない場合は、特に処置を行わず経過を観察することもあります。ただし、見た目には正常に見えていても、かみ合わせがズレていたり、将来的にむし歯や炎症を起こしたりするリスクがあるケースも少なくありません。
「痛みはないけど違和感はある」「風邪をひくと鈍い痛みが出る時がある」といった軽い症状でも、放置せずに一度歯科医院でチェックを受けるようにしましょう。
斜めに生え、一部が見えている親知らず(半埋伏智歯)
 親知らずが斜めに生えて、一部だけが歯ぐきから見えている状態を「半埋伏智歯(はんまいふくちし)」といいます。このタイプの親知らずは、表面が露出していても奥まった位置にあるため、歯ブラシがきちんと届きづらく、汚れが溜まりやすいのが特徴です。
親知らずが斜めに生えて、一部だけが歯ぐきから見えている状態を「半埋伏智歯(はんまいふくちし)」といいます。このタイプの親知らずは、表面が露出していても奥まった位置にあるため、歯ブラシがきちんと届きづらく、汚れが溜まりやすいのが特徴です。
清掃が不十分になりやすいため、周囲の歯ぐきが腫れたり、繰り返し炎症を起こしたり、口臭の原因になることもあります。炎症を放置すると、隣接する歯に悪影響を及ぼすこともあるため、トラブルが出ている場合や今後のリスクが高い場合には、抜歯を検討します。
横向きに埋まっている親知らず(水平埋伏智歯)
親知らずが完全に歯ぐきの中に埋まり、さらに真横を向いている状態を「水平埋伏(すいへいまいふく)」といいます。主に下顎の親知らずに見られるパターンで、手前の歯の根にぶつかって圧迫していたり、歯並びやかみ合わせに悪影響を与えたりする恐れがあります。
このタイプの親知らずは抜歯の際に、歯ぐきの切開や顎の骨を削る必要になる場合があり、手術の難易度が高くなります。歯科用CTでの精密な診断をもとに、慎重に判断・処置を行います。
親知らずの抜歯後の腫れ・痛みの期間
親知らずの抜歯後、麻酔は通常3〜4時間ほどで効果が切れてきます。それに伴い痛みが出はじめるため、事前に痛み止めを服用しておくと、痛みを和らげやすくなります。
痛みのピークは一般的に翌日〜2日後、腫れは3〜4日後に強くなる傾向がありますが、どちらもその後は徐々に落ち着いていきます。多くの場合、1週間ほどで痛みはほとんど感じなくなり、通常の生活に戻ることができます。
ただし、傷口が大きかったり、骨を削るなど外科的処置を伴ったりするケースでは、痛みや腫れがやや長引くこともあります。そのため、必要に応じて翌日に傷口の確認を行うこともあります。気になる症状や不安なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
抜歯当日にしない方が良い7つのこと
① 強いうがい
抜歯後すぐは、うがいのしすぎに注意が必要です。強くうがいをすると、傷口にできた血のかたまり(血餅)が取れてしまい、治りが悪くなる可能性があります。口の中に血が溜まって気になる場合は、軽く吐き出すか、滅菌ガーゼをそっと噛んで止血しましょう。
② 傷口の歯みがき
当日は抜歯部位に歯ブラシを当てず、軽く口をゆすぐ程度にとどめてください。翌日からは歯磨きを再開できますが、縫合してある場合は、糸に歯ブラシが引っかからないよう注意しましょう。
③ 冷やしすぎ
腫れが気になっても、氷などで冷やしすぎるのは逆効果です。過度な冷却で血流が悪くなると、かえって治癒が遅れてしまうこともあります。冷やす場合には、濡らしたタオルで優しく冷やす程度にしましょう。
④ 舌や指で触れる
歯を抜いた穴を舌で探ったり、指で触れたりすると、血餅が取れやすくなり治癒に悪影響を及ぼします。気になるかもしれませんが、なるべく患部には触れないようにしてください。
⑤ 激しい運動
運動によって血流が活発になると、再び出血する可能性があります。当日は安静に過ごし、無理な運動は控えてください。
⑥ 長風呂や熱いお湯
長時間の入浴や熱いお風呂も、血行が促進され出血しやすくなるため控えましょう。なるべくシャワーだけにとどめておくと良いです。
⑦ 喫煙・飲酒
喫煙は毛細血管を収縮させ、治癒を妨げるだけでなく、感染のリスクも高めます。また、飲酒も血行を促進し、出血の原因になりやすいです。少なくとも数日間は控えることをおすすめします。
親知らずの抜歯の流れ
 トワデンタルクリニック人形町で行っている、「親知らずの抜歯の流れ」を説明します。
トワデンタルクリニック人形町で行っている、「親知らずの抜歯の流れ」を説明します。
当院では、わかりやすく丁寧なカウンセリングを行っていますので、ご不明な点は受診時にお尋ねください。
埋まっている、横向きになっているなどの複雑な生え方をしている親知らずの抜歯も対応可能です。まずはご相談ください。
1検査とカウンセリング
レントゲンや歯科用CTを撮影し、親知らずの状態や周辺の血管・神経の位置などを確認します。
検査結果を一緒にモニターで見ながら、抜歯の必要性や抜歯の難易度、リスクなどについてもわかりやすくご説明します。
検査をしてすぐに抜歯することはありませんのでご安心ください。説明を聞いた上でゆっくりとご検討いただけます。
また、健康状態や服用中の薬などもお聞かせください。
2親知らず周辺に麻酔を行います
抜歯をする親知らずの周辺に麻酔をしてから抜歯を行います。
できる限り痛みに配慮して治療を進めますので、不安なことがあればお気軽にご相談ください。
3親知らずの抜歯
お身体の状態によっては、血圧や心拍数を測定して全身の健康状態を確認しながら治療を始めます。
歯ぐきに埋まっている親知らずの場合は、歯ぐきの切開を行い、生え方によっては歯を小さく砕いてから抜歯を行います。
4縫合と止血
抜歯が完了したら傷口の縫合を行います。縫った後は消毒し、ガーゼを噛むなどして止血を行います。
止血されてから、今後の注意点などをご説明します。
ご自宅での過ごし方や食事の心配ごとなど、どのようなことでもお尋ねください。
5抜糸
親知らずの抜歯を行うと、お口周りが腫れたり痛みが生じることがありますが、1週間ほどでおさまる方がほとんどです。
痛みが引かなかったり痛みが悪化した場合は早めにご連絡ください。
手術をしてから約1週間後に抜糸を行います。
ご自身の歯を移植する「自家歯牙移植」
自家歯牙移植は、ご自身の口の中にある健康な歯を、別の場所に移して機能を補う治療方法です。たとえば、親知らずなど噛み合わせに影響の少ない歯を、むし歯や外傷などで歯を失った部分へ移植するケースが多く見られます。
移植に使う歯がご自身のものであるため、身体へのなじみが良く、異物感も少ないのが大きな特長です。
また、人工物を使う治療と比べて、生体との適合性が高く、自然な噛み心地を得やすいというメリットもあります。
自家歯牙移植は以下のようなケースで検討されることがあります。
- むし歯や歯周病で抜歯が必要になった場合
- 外傷などで歯を失ってしまった場合
- 機能的に影響のない位置に健康な歯(例:親知らず)がある場合
インプラントやブリッジとは異なり、自分の歯を活かすことができる治療法です。レントゲンやCTによる事前の診査や適用条件がありますので、まずは一度ご相談ください。
「自家歯牙移植」のメリット
自分の歯を使えるという安心感
自家歯牙移植の大きなメリットは、ご自身の歯を移植に使えることです。人工物ではなく、自分の身体の一部である歯を利用するため、心理的なハードルが下がり、治療に対する安心感が得られやすくなります。移植した歯に対する身体のなじみも良く、アレルギーや異物感のリスクが少ないことも利点です。
高い生体適合性と定着のしやすさ
人工物ではなく自分の歯を用いることで、移植後の生着がスムーズに進みやすくなります。特に、自家歯牙移植では「歯根膜」という組織も一緒に移されるため、この部分が骨と自然に結合し、定着が安定しやすいという特長があります。インプラントのような拒絶反応の心配がないのも大きなメリットです。
噛み心地が自然で違和感が少ない
自分の歯を使うからこそ、治療後の噛み心地が自然で、違和感がほとんどありません。咀嚼時の力のかかり方や感覚も、自分の歯そのものと近く、食事や会話を快適に楽しむことができます。特に硬いものを噛んだときなど、人工物では得られない自然な感覚を取り戻せることもこの治療法の魅力です。
自家歯牙移植を適用できる条件
自家歯牙移植は、すべての方に適用できる治療ではありません。以下のような条件を満たしている場合に、治療の選択肢として検討されます。
移植に使える健康な歯があること
移植元として使える歯があるかどうかが第一条件です。多くの場合、かみ合わせに影響を与えていない親知らずなどが移植に適しています。すでに役割を終えている歯が口腔内に残っていれば、それを有効に活用できます。
歯根膜がしっかり残っていること
移植の成功には「歯根膜(しこんまく)」の存在が欠かせません。歯根膜は、歯と骨の間をつなぐ組織で、骨と自然に結びつく働きをします。移植時に歯根膜がうまく保存できていれば、定着もスムーズに進みやすくなります。
移植する歯と移植先のサイズが合っていること
移植元の歯と、移植先のスペースの大きさが異なると、安定性に影響が出てしまいます。サイズや形のバランスがとれていることも、適応の判断材料となります。
・歯の根っこ(歯根)が単純な形であること
移植する歯の根っこが極端に曲がっていたり、複雑な形をしたりしている場合、抜歯時に歯根膜を傷つけてしまう可能性があります。歯根の形状がシンプルであることも、適応の重要な判断材料の一つです。
当院の自家歯牙移植
衛生管理が徹底された完全個室の「オペ室」完備
 当院は、一般的な診療室とは別に外科処置を行う完全個室の「オペ室」をご用意しています。
当院は、一般的な診療室とは別に外科処置を行う完全個室の「オペ室」をご用意しています。
安全な外科処置を行うための設備
 当院は、顎骨・血管の状態、歯と神経の位置関係を3次元画像で取得することが可能な「歯科用CT」を用いた精密検査ができます。
当院は、顎骨・血管の状態、歯と神経の位置関係を3次元画像で取得することが可能な「歯科用CT」を用いた精密検査ができます。
そのため、より患者様の負担を軽減した治療計画の立案につながります。また、万が一の事態に備えてAEDなども完備しています。